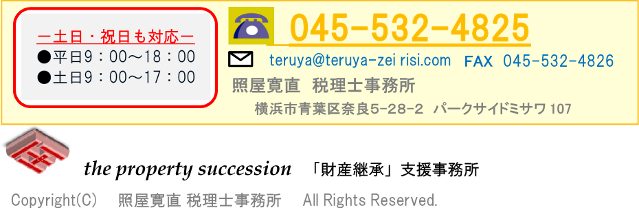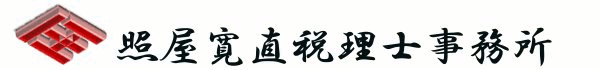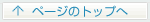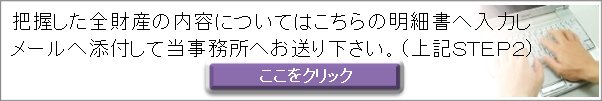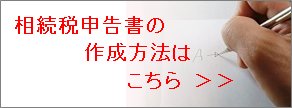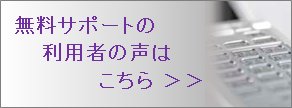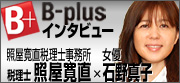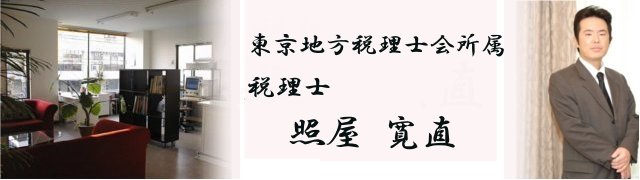
�Ɩ����e�@�F�@�����Ő\�����쐬�̖����T�|�[�g�̊T�v
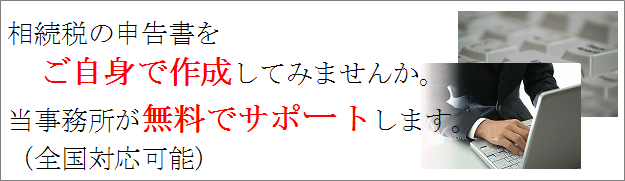
�Ɩ����e�@�ڎ�
�����g�ő����Ő\�������쐬����ꍇ�̖����T�|�[�g�T���}
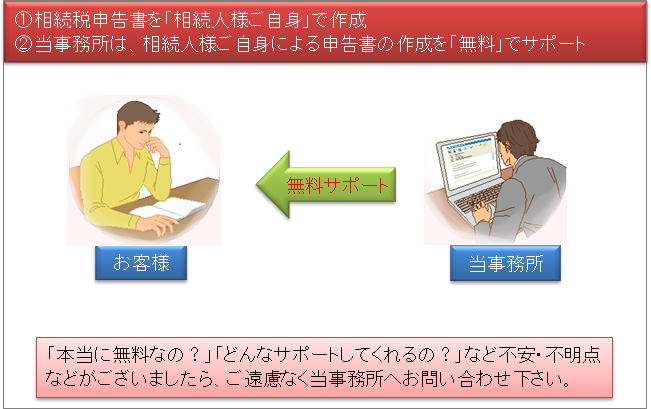
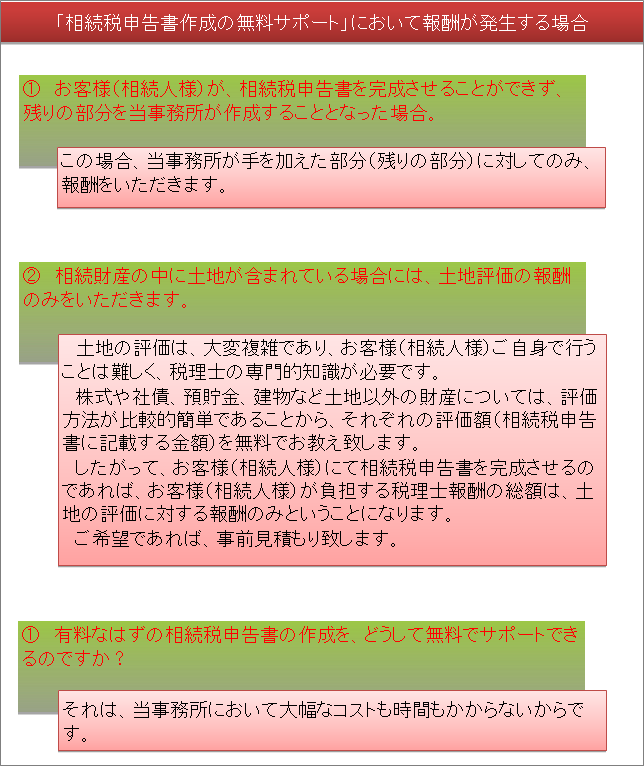
�����Ő\�����̍쐬�͒N�ɂł��ł��܂�
�����Ő\���̐ŗ��m�ւ̕�V�͂قƂ�ǂ̕��������Ǝv���Ă���悤�ł��B
��V����������\�����̍쐬�͓���Ƃ�����ł͕K����������܂���B
�������Y�̓��e�ɂ���Ă͑����l�����g�ō쐬���\�ȏꍇ������܂��B
�������A�����ł̐\�����ɂȂ��݂��Ȃ�����ł��傤���A�����ō쐬����Ƃ����s���ɂ͂Ȃ��Ȃ�����
�Ȃ��悤�ł��B
��ނɂ���ẮA�\�����ւ��������ʂ������Ƃ������Y������܂��B
�Ⴆ�A�a���A�����A���S�ی����A���������A�ؓ����A��������Ô�E�E�E�E�E�ȂǁB
�L���،����قړ��l�ŁA������Ƃ����|���Z�ŕ]���z���Z��ł���̂ł��B
�����āA���̕]���z��\�����L�ڂ���Α����Ő\�����̊����ł��B
�ł����A�������Y�̋L�ڏꏊ�𑊑��Ő\�����̒�����T���̂͑f�l�ɂƂ��đ�ςȍ�Ƃł��B
�����ŁA���Y�̕]���z�A�����Ő\�����̋L�ڕ��@�i�����Ő\�����̏������j�ȂǑ����Ő\������
�����܂ŁA���[����ʂ������ŃT�|�[�g�v���܂��B
�i�@�����Œ��ӂ��Ă������������̂́A���Y�ɓy�n���܂܂�Ă���ꍇ�ɂ́A�y�n�̕]���ɂ��Ă�
���I�m����v����̂ŁA�y�n�̕]���݂̂͗L���ƂȂ�܂��B�j
�Ȃ��ɂ́A�u�r���܂ł͎����ō쐬�ł������A���̐�͕��G�����Ă�����ƁE�E�E�v�u���̐�͎��Ԃ��Ȃ���
�����Ő\�����̍쐬�͖����v�Ƃ������ɂ��܂��ẮA���������ɂĐ\�����̎c��̕�����
�쐬�v���܂��B�i�L���j
�������A����������V�͓�����������������쐬���������݂̂ł��B�i��V�̏ڍׂ͎��O�ɖ����v����
���B�j
�u�����ʂ������Ȃ玩���ō쐬���Ă݂����v�u�����ł̐\����V�͍��z������Ǝv���v�Ƃ������A
�ŗ��m�ֈ˗������Ɏ������g�̎�ő����ł̐\�����쐬���Ă݂܂��B
��L�̒m���͈�ؕK�v����܂���B
����]�̕��́A���������ւ��₢���킹���������B
�����Ő\�����쐬�̖����T�|�[�g�́A�u���łɈ�Y�����̘b���������ς�ł���v�@�܂��́@�u�����l
�ǂ������������ƂȂ���Y�������ł���v���Ƃ��O��ƂȂ�܂��B
��Y�����ɑ�������������悤�ł���Εٌ�m�܂��͎i�@���m�֑��k���A���̌�A��Y�������c��
�����܂�����A�u�����Ő\�����쐬�̖����T�|�[�g�v�����v���܂��B
�ٌ�m�܂��͎i�@���m�̒m�荇�������Ȃ����ɂ��܂��ẮA���{�S���A���ꂼ��̒n��ɖ�������
���Ƃ����Љ�v���܂��B
�����g�ő����Ő\�������쐬����ꍇ�̍�Ƃ̎菇
���Y�̒��ו�����A�����Ő\�����̍쐬�܂ł��ł�����̂ł����A���̍ۂ̏����Ƃ��āA
�����g�Ń��[���̑���M�����邱�Ƃ��ł���K�v������܂��B
�@�@�@�@�@�����������́u�����Ő\�����쐬�����T�|�[�g�v�ɂ����ẮA���[���̂�����
�@�@�@�@�@�@�l���R�����ɏ\���z�����A���m�s�s�f�[�^���Í������[���\�t�g���g�p�v���܂��B
�@�@�@�@�@�@���̃��[���\�t�g�͖����ɂĂ��v���܂��B
�����g�Ń��[���̑���M���ł��Ȃ����ɂ��ẮA���[���ɑ���e�`�w��X�ւ��g���Ă̂���肪
�\�ł��B
���̍ۂɔ�������X�����̔�p�ɂ��Ă͂��q�l���S�ƂȂ�܂��̂ł������������B
�e�`�w��X�ւł̐\�����쐬�����T�|�[�g����]�̕��́A���������ւ��A���̍ۂɂ��̎|�������������
�������B
��Ƃ̎菇�Ƃ��Ď��́u�Q�p�^�[���v��p�ӂ��Ă��܂��B
�P�D���Y�z���u���q�l�������Ő\�����L�ځv����ꍇ�̐\�����쐬�̗���
![�푊���l�̑S���Y��c�������� �c�������S���Y�̓��e�������ւ����[���ɂĒʒm �����Ő\�����ւ̑S���Y�̋L�ڏꏊ���w�� ���q�l�ɂāA���Y�̕]���z�𑊑��Ő\�����L���i�\�����̍쐬�j ���q�l�ɂāA�Ŗ����\�������o�y�є[��](img/nagare1.jpg)
����L�̍�ƕ��@���킩��Ȃ��ꍇ�́A���̓s�x���d�b�܂��̓��[���ɂĂ������������܂��B
�@�@����L�̑S��Ƃ������ɂĒ������܂��B�i�y�n���������̏ꍇ�A�y�n�̕]���ɂ��Ă�
�@�@�@ �L���ł��B�j
�P�D�܂��́A�����܂��ɍ��Y��c�����܂��B�@�c���̎d����������
�Q�D�����܂��ɍ��Y��c��������A���͂������Y�̋��z�Ȃǂ̏ڍׂׂ܂��B
�@�@�@�@�@�@ �h���Y�h�̋��z�ׂ邽�߂̏��ނƂ��̎擾��͂�����@���@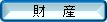
�@�@�@�@�@�A �h���h�̋��z�ׂ邽�߂̏��ނƂ��̎擾��͂�����@���@
�@�@�@�@�@�B �h������p�h�ƂȂ���z�ׂ邽�߂̏��ނ͂�����@�@���@�@�@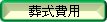
�@�@�@�@�@�C �\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��h���O���^�h�̒��ו��͂�����@�@���@�@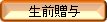
�Q�D���Y�z���u���������ɂĐ\�����L�ځv����ꍇ�̐\�����쐬�̗���
![�푊���l�̑S���Y��c�������� �c�������S���Y�̓��e�������ւ����[���ɂĒʒm �����Ő\�����ւ̑S���Y�̋L�ڏꏊ���w�� ���q�l�ɂāA���Y�̕]���z�𑊑��Ő\�����L���i�\�����̍쐬�j ���q�l�ɂāA�Ŗ����\�������o�y�є[��](img/nagare2.jpg)
����L�̍�ƕ��@���킩��Ȃ��ꍇ�́A���̓s�x���d�b�܂��̓��[���ɂĂ������������܂��B
�@�@����L�̑S��Ƃ������ɂĒ������܂��B�i�y�n���������̏ꍇ�A�y�n�̕]���ɂ��Ă�
�@�@�@ �L���ł��B�j
�P�D�܂��́A�����܂��ɍ��Y��c�����܂��B�@�c���̎d����������
�Q�D�����܂��ɍ��Y��c��������A���͂������Y�̋��z�Ȃǂ̏ڍׂׂ܂��B
�@�@�@�@�@�@ �h���Y�h�̋��z�ׂ邽�߂̏��ނƂ��̎擾��͂�����@���@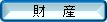
�@�@�@�@�@�A �h���h�̋��z�ׂ邽�߂̏��ނƂ��̎擾��͂�����@���@
�@�@�@�@�@�B �h������p�h�ƂȂ���z�ׂ邽�߂̏��ނ͂�����@�@���@�@�@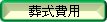
�@�@�@�@�@�C �\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��h���O���^�h�̒��ו��͂�����@�@���@�@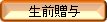
�����l�����g�ő����ł̐\���������ꍇ�̐Ŗ������ɂ���
�����ł́u�Ŗ������v�́A���v�ɂ��Ƒ������Y��3���~����ΕK���Ƃ����Ă����قǂ���悤
�ł��B
�Ŗ������̎����͐\�������Ă���P�`�R�N�オ��ʓI�ŁA�s��ꂽ�Ŗ������̂����A8������9����
�\���R����w�E����Ă��܂��B
���́u�Ŗ������v�ɂ����Ďw�E���ꂽ�\���R���60���͌��a����L���،��Ȃǂ̋��Z���Y�ƂȂ���
���܂��B
���̂��Ƃ���u�Ŗ������v�͋��Z���Y���d�_�I�ɒ��ׂ�X���ɂ��邱�Ƃ�������܂��B
�����ł́u�Ŗ������v���s���ꍇ�A�����l�̑�\�i�Ǝv������A���͑����Ő\�����ɏ����i�T�C���j
�����ŗ��m�֎��O�ɘA��������܂��B
����̂悤�ɁA�ŗ��m�������ł̐\�������쐬����̂ł͂Ȃ��A�����l���g�ő����ł̐\�����̍쐬
���s���ꍇ�́A�����ł̐\�����ŗ��m�̏����i�T�C���j������܂���̂ŁA�����l�̒��ő�\�i��
�v������֘A��������܂��B
�u�Ŗ������v�͐ŗ��m�̗�������K�v�Ȃ̂ŁA���̍ۂɂ́A�u�ŗ��m�̗���̉��ł̐Ŗ�����
����]����v�|��Ŗ����֓`����Ɠ����ɓ��������ւ����A���������B
����ȍ~�͓����������A���q�l�ƐŖ����Ƃ̊Ԃɗ����A�u�Ŗ������v�̓����Ȃǂ̂������A�Ŗ���
�Ƃ̊Ԃōs���܂��B
�����܂�ɂł����A���O�A�����Ȃ��������K�₷�邱�Ƃ�����܂����A���̍ۂɂ͂���Ă��Ɂu�ŗ��m��
����̉��ł̐Ŗ���������]����v�Ƃ������Ƃ����ɓ`���A����̒��ւ͓���Ȃ��ʼn������B
���̍ۂɁA���������֘A�����Ă���������A�O�őҋ@���Ă��钲�����Ɠ������������ډ����܂��B
�Ŗ������̃|�C���g�i�\���R����Ȃ������߂Ɂj
�Ŗ������d�_�I�ɒ��ׂ錻�a���ɂ��ďq�ׂ܂��B
�������́A�S���Ȃ������i�푊���l�j�̐��O�̎����̋K�͂ɉ����āA�u���ꂾ���̎���������A
���S���_�ł́A�ʏ�A���Y�͂��ꂾ���c���Ă���ł��낤�v�Ɛ��肵�A���̐���z�Ƒ����Ő\���ɋL��
����Ă�����Y�z�Ƃ��r���A�ǂꂾ���̍��ق����邩�ɂ��\���R��̗L���������܂��ɔ��f���܂��B
���O�̎������z�́A�ߋ��ɐŖ����֒�o���������ł̊m��\��������c�����Ă��܂��B
���̂ق��A�S�Ă̗a�����A�����ԁi��3�N����5�N���j�����̂ڂ��ē��o���̓�����ǂ��A�����o����
���������Ɏg�������A���͑����l�̎�ɓn���ĂȂ����ȂǁA�a���̂������ŏI�I�ɉ��ɕς�����̂��A
�ǂ��ɑ��݂���̂������ǂ��Ă����Ē��ׂ܂��B
�܂�A�����o���ꂽ�a���̒ǐՒ������s���A���̈����o���������Łu�����w�������̂��v�܂��́u�N��
���^�����̂��v�Ƃ����悤�ɁA�����̍ŏI�̓��B�_�͂ǂ��������A�܂��͒N�̎�Ȃ̂��ׂ�Ƃ�������
�ł��B
�Ŗ������ɂ����ē��ɒ��ׂ���̂��A���`��a���̑��݂ł��B
���`��a���Ƃ́A�a���ʒ��̖��`�͎q�⑷�Ȃǂ̖{�l�ȊO�̐l�Ԃł��邪�A���ۂ̏��L�҂�
�푊���l�ł���a���̂��Ƃł��B
���`��a�����ǂ����̂����܂��Ȕ��f�̃|�C���g�Ƃ��āA���`�l�ƂȂ��Ă�����i�q�⑷�j�̎�����
�K�͂ɑ��A���̎����ł���Βʏ�A�ǂ̒��x�̒��~���\���ǂ����ł��B
���̂ق��̖��`��a���̔��f�|�C���g�Ƃ��āA�a���ʒ��y�ш�ӂ�N���Ǘ����Ă����̂��ł��B
�a���ʒ��y�ш�ӂ�푊���l���Ǘ����Ă����ƂȂ�ƁA�q�܂��͑����`�̗a���́A�푊���l�����L��
�Ă����a���ƒf�肳��܂��B
����ɓ˂��l�߂�ƁA��s�ɕۊǂ���Ă�������J�݂̍ۂ̐\�����̕M�Ղ��푊���l�ł��邩�ǂ�
�������f�ޗ��ɂȂ�܂��B
���̂ق��A�Ŗ������̍ۂɒ������͂��肰�Ȃ��Ƃ̒����ώ@���A��s��،���Ђ̖��O���������J����
�_�[��^�I���ȂǁA�����J�݂��������Ɛ���ł��镨���Ȃ����ǂ������Ă��܂��B
������Z�@�֓��𐄒�ł�����̂Ƃ��āA�J�����_�[�A�^�I���A�N���A�ƒ�̓d�b���A���T���A�F��
�L�^�A�����Ȃǂ�����܂��B
�������͗a���ʒ����ӂȂǂ̏d�v�Ȃ��̂��ۊǂ���Ă���ꏊ�i���ɂȂǁj�̊m�F�����܂����A����
�ꏊ�ɂ͑����l�̈�ӂ���ȂǁA�푊���l�̕��ȊO��ۊǂ���Ɩ��p�ȋ^�f��������̂ŁA
���S��ɐ�������ۂɂ͑����l�̕����ꏏ�ɂ��Ȃ��悤�ɂ��ĉ������B
�������́A���X�̗a���ʒ��̈����L�^������ɂ̑��݂�c�����܂��B
�܂��A����̐������M��Ȃǂ̂悤�ɁA���R����ׂ��������Ƃ�������Ă���a���ʒ����Ȃ��ꍇ�ɂ�
�ʒ��̉B�����w�E���Ă��܂��B
���̂悤�ɒ������͂���܂ł̌o������ʂ��A����Ƃ�������̂���\���R������A�ŋ���lj���
��������̂ł��B